岡山県内には歴史的な町並みが今も残る地区がいくつもあります。高梁市吹屋、津山市城東・城西地区などがあり、その中でも代表的なものが倉敷美観地区です。
足守の町の起源は江戸時代に栄えた「陣屋町」。
町ができたきっかけには、歴史を左右した大合戦や、それに翻弄された武将親子が関わっているのです。
他にも、足守には後楽園に並ぶ大名庭園があったり、日本文化の発展に貢献した偉人たちを輩出したり、実は歴史観光の穴場スポットなのです。
※文中で「足守」は足守陣屋町周辺エリア、「足守地区」は旧足守町エリアを指します
古代からその名が見える足守。備中高松城の水攻めにも関わりが……
足守の地名はかなり古くから存在していたとみられ、日本最古の歴史書とされる『日本書紀』にも出てくるほど。
戦国時代に突入すると防衛拠点として「境目七城(さかいめ しちじょう)」のうち宮路山城・冠山城が足守地区内に築かれ、「備中高松城の水攻め」にも関わりました。
※参考:備中高松城水攻め
豊臣秀吉とも関係の深い大名親子の決断が関ヶ原の戦いの運命を変えた!?
なぜ足守に陣屋町が生まれたのでしょうか。歴史をたどると、その発端は関ヶ原の戦いにありました。キーパーソンとなるのが、木下家定(きのした いえさだ)と小早川秀秋(こばやかわ ひであき)の2人です。
豊臣秀吉の正室「ねね(高台院、北政所)」の兄で、秀吉の義兄にあたる人物。そして小早川秀秋の父。
木下家定の五男。「ねね」の甥で、秀吉の義理の甥。秀吉の養子となり、一時は天下人後継者のひとりとなるも、のち小早川隆景の養子となった。
慶長5年(1600年)、天下分け目の「関ヶ原の戦い」を控え、秀秋は石田三成率いる西軍につきます。父家定は、西軍・東軍にも属さない「中立」の立場でした。
しかし秀秋は合戦で、その後の歴史を動かす決断をし東軍に鞍替えしたことで、徳川家康率いる東軍が勝利。家定は最後まで中立を貫きました。
- キジ
家康が家定に対して「元大将・秀吉の正室であるねねを、兄である家定が護衛しろ。だから京都から動くな」と命じたんだ。ただ、それは表向きの理由で、おそらく少しでも西軍が有利な状況を作らせないのが本心だろうね。もし、ねねが西軍についたら後に続く人が出るだろうから。
- サル
家定は自分の意志だけで中立を選んだのではないんじゃな。
一方で諸説ある秀秋の行動ですが、近年の研究により詳細が見えてきたのです。東軍の武将の手紙に、関ヶ原の戦い開始前に秀秋が東軍側につく意志を示したという内容が見つかりました。そして合戦の序盤で早くも東軍側についた可能性が高いのです。
秀秋は東軍の武将による説得と、西軍の武将への配慮の間で心が揺れ動き、開戦前まで立場を決めかねていたと思われます。東軍による粘り強い説得が、秀秋を決心させたのでしょうか。そして合戦後、秀秋は家康に功績を称えられ、備前岡山城主になりました。
※参考:岡山城と城下町の形成
家定は、合戦前には姫路城主でしたが、合戦後の慶長6年(1601年)に備中国の南東部の領地を与えられました。そして足守に拠点を構えたといわれ、これが「足守藩」の成立とされます。
- キジ
家定が備中へ領地替えとなったのは、岡山より西側には関ヶ原の戦い時に西軍側だった、家康が信用のおけない外様大名が多くいたからなんだ。江戸幕府に刃向かう連中が岡山へ攻め込まないよう、足守の近くを通る交通の要・西国街道を押さえられ、にらみを利かせるため家定に備中南東部の領地を与えたともいわれているんだよ。
- キジ
秀秋が城主の岡山城下は、足守から備前・備中国境を挟み直線で13km程の距離。息子がピンチの時、すぐさま駆けつけられるよね!
- サル
親子の絆が加われば守りがより強固になると考えたのも家定を選んだ理由じゃろな!
- キジ
でも残念ながら秀秋は、岡山城主になって2年弱、21歳の若さで亡くなったんだよ。
秀秋が城主であった期間は短かったものの、岡山城の近代化改修や検地など、今に繋がる業績も残しています。
早世した秀秋には跡取りがおらず、その後の岡山は池田家が治めていくことになります。
足守陣屋町は城下町の小規模版?江戸時代の面影を探してみよう!
初代藩主・家定は慶長13年(1608年)に死去しますが、家康の思惑により木下家は領地を没収されてしまいます。元和元年(1615年)に元の領地を回復して以降、幕末まで木下家が治めました。
足守陣屋町が整備されたのは江戸時代からで、それより前は足守の北にある大井(現 北区大井)が地域の中心だった
足守が領地の中心的な町である陣屋町として本格的に整備されたのは、寛永14年(1637年)ごろからです。
- キジ
陣屋町とは陣屋(領地支配の拠点となる館)を中心に形成された町。城をもたない大名などが陣屋を構えたんだよ。
町の西部に陣屋が建てられ、侍屋敷町も造られました。東部は商人や職人の住む町人町に。小規模な町ながら「武士の町(武家屋敷ゾーン)」と「商工業者の町(町家ゾーン)」の二つの顔が併存している点が足守陣屋町の特徴です。
- キジ
陣屋町の区画は現在の区画と重なっていて、当時の面影が感じられるよ!
県を代表する大名庭園の一つ近水園は美しい池と吟風閣の景観が魅力
江戸時代の名残が感じられる足守ですが、中でも屈指のスポットが大名庭園「近水園(おみずえん)」です。
近水園は岡山市の後楽園、津山市の聚楽園(しゅうらくえん)と並ぶ岡山県を代表する大名庭園の一つで、岡山県の名勝に指定されています。
近水園は江戸時代中期までに造園されたと推測されています。見どころは、池と吟風閣(ぎんぷうかく)。池は足守川から水が引かれていて、鶴島と亀島を配置しています。
- キジ
近水園は庭園造りの名人だった小堀遠州が得意としたような池泉回遊式庭園(池の周囲を歩きながら楽しめる庭園)だよ。
吟風閣は宝永5年(1708年)に、当時の藩主が幕府により京都御所の工事を命じられた時、余った資材を持ち帰って建築しました。
- キジ
美しい池と吟風閣の景観は、近水園の象徴。ぜひこの美しい景色を写真に収めてみて!
- サル
春には桜、秋には紅葉の名所として四季折々の美しい景観が楽しめるんじゃ。
足守が生んだ、歴史に名を刻む2人の偉人に迫る
実は足守では、この地で生まれ育ったり、ゆかりのあったりした人物が、多く活躍しています。
- キジ
中でも代表的な足守出身の人物は、緒方洪庵(おがた こうあん)と木下利玄(きのした りげん)の2人だね。
- イヌ
僕は知らないから、どんな人たちなのか教えてほしいワン!
緒方洪庵 〜 天然痘治療やコレラ治療で功績を残した「日本近代医学の祖」
緒方洪庵は、江戸時代後期に足守藩士の三男として生まれました。少年時代に足守で細菌性感染症のコレラが発生し、医学の道を志すようになったといわれています。
天保9年(1838年)に大坂(現在の大阪)で医院を開業すると同時に、蘭学塾「適塾(適々斎塾)」を開きました。さらに足守の葵ヶ丘除痘館(足守除痘館)をはじめ、大坂や江戸に除痘所(天然痘の予防・治療を行う施設)を開設、またコレラ治療法を記した書物を出版するなどしました。
- キジ
洪庵は天然痘治療やコレラ治療で功績を残したことから「日本近代医学の祖」とも呼ばれているんだ。
- キジ
適塾は、江戸時代後期や明治時代に政治・経済・医療・学問など各界で活躍した人物をたくさん輩出したんだ。とくに著名な洪庵の門下生には、福澤諭吉がいるよ。
洪庵はその後、幕府の要請により江戸の西洋医学所で医師として活躍し、後身の育成にも尽力しました。そして文久3年(1863年)に江戸で54歳の生涯を閉じます。洪庵の精神は息子や親族に受け継がれ、彼らが活躍した大坂の浪華仮病院・仮医学校は、現在の大阪大学のルーツとなりました。そのため大阪大学の源流は、洪庵と適塾にあるともいえるでしょう。
木下利玄 〜 足守藩主の家系に生まれた歌人
木下利玄は明治19年(1886年)、足守で旧足守藩主・木下利恭(きのした としもと)の甥として生まれ、歌人として活躍しました。歌人・佐佐木信綱のもとで短歌を学び、志賀直哉や武者小路実篤らとともに文学誌『白樺』の創刊にも関わります。
- キジ
利玄の作品は口語や俗語を使用した平易なものが特徴で、「自然描写と感情の融合」を得意としていたんだ。「利玄調」と呼ばれる独自の作風だよ。
足守観光駐車場に建つ利玄の歌碑「曼珠沙華 一むら燃えて 秋陽つよし そこ過ぎている しづかなる径」
- キジ
足守観光駐車場に建つ利玄の歌は、故郷・足守に帰ってきて歌ったとされているよ。
- サル
もしかしたら、足守川の土手に咲くヒガンバナ(曼珠沙華)を見て歌ったのかもしれんのぉ!
近水園に建つ利玄の歌碑「花びらをひろげ疲れしおとろへに 牡丹重たく 萼をはなるる」
利玄は歌集の発刊や文学運動への参加を行うなど、短歌の道を究めていきますが、大正11年(1922年)肺結核に罹患。病床でも短歌を詠み続けますが、大正14年(1925年)に40歳の短い生涯を閉じました。口語や俗語を使用した利玄の歌は、同時代や後世の歌人から高い評価を得ています。
多くの偉人を輩出し、ゆかりがある人も多い足守
洪庵・利玄のほかに活躍した足守出身・ゆかりの人物を紹介します。
◆栄西(ようさい):鎌倉時代の禅僧で、茶の普及に尽力。重源の死後、東大寺再建の仕事を引き継いだ。
※参考:東大寺再建瓦と偉人たち
◆寂厳(じゃくごん):江戸時代後期の僧侶・書家。
◆藤田千年治(ふじた せんねんじ):江戸時代後期に活躍した商人。足守で醤油醸造を始めた。
◆安富才助:江戸時代後期に足守で生まれた足守藩士で、新撰組隊士。田上寺に墓がある
- キジ
安富才助(やすとみ さいすけ)は、20代で新撰組に入隊。土方歳三の右腕として活躍し、厚い信頼を得たんだよ。 戦死した土方歳三の最期を看取ったとされているんだ。戊辰戦争の時、斎藤一に次ぐ副長役に任命されるなど、活躍したんだ!
- サル
あの土方歳三に認められるとは、かなりの凄腕じゃったんじゃなぁ。
- イヌ
すごい人たちが、こんなにたくさん居ただなんて、驚きだワン!
足守歴史庭園には足守にゆかりのある人の銅板が掲示されています。
岡山市唯一の町並み保存地区として
足守陣屋町の町並みは1990年(平成2年)に岡山県指定町並み保存地区となり、本格的に町並み保存へと動き始めました。
- キジ
旧陣屋町エリアには江戸時代の伝統的家屋の面影が残る家屋が今も多いんだ!一般民家の改修も景観を損なわないような改修が進められているよ。
- サル
洪庵や利玄が暮らしとった町並みを歩けるんじゃな!どんな特徴の町なんじゃ?
- キジ
一番の特徴は、旧陣屋町が今も住民の生活の場となっていること。観光目的でだけはない、生活に根付いた町並みや雰囲気が足守の魅力だね!
- イヌ
今でも江戸時代の町並みを感じられるだなんて、素敵だワン!
- キジ
足守では観光駐車場が無料なんだ。 観光施設も入場無料のところが多く(提供サービスは除く)、近水園も入園無料だよ(吟風閣は除く)。岡山桃太郎空港や岡山総社ICから近いのもポイント!



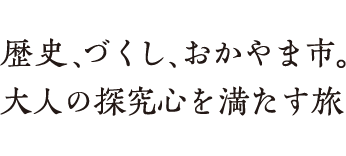






























































































安政2年(1855年)〜安政5年(1858年)のあいだ福澤諭吉は適塾に通い、洪庵の下で蘭学を学んだ。最年少の22歳で適塾の塾頭になるなど、勉学に励んだという。